Twelve tips to optimize group decision-making in medical education: ‘Tipping’ the scales toward wisdom of the crowd and minimizing groupthink
Lea Harper,Omid Kiamanesh,Sylvain Coderre,Kenna Kelly-Turner,Melinda Davis &Kevin McLaughlin
Received 16 Dec 2024, Accepted 27 Mar 2025, Published online: 09 Apr 2025
Cite this article https://doi.org/10.1080/0142159X.2025.2488326
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0142159X.2025.2488326?af=R
グループでの意思決定は、医学教育において一般的なものとなっており、研修生を昇格させるか再教育するかといった、複雑かつ利害関係の大きい意思決定に用いられることが多い。 このような状況では、集団での意思決定の方が個人での意思決定よりも優れており、集合的な知識と経験の蓄積によって質の高い意思決定結果が得られると思われがちである。 しかし、集団が個人を凌駕することはあっても、それが保証されているわけではない。 実際、集団は、個人にはないいくつかの認知バイアスやプロセスの問題にさらされやすく、これらを管理しなければ、質の低い意思決定結果につながりかねない。 集団での意思決定に参加する教育指導者として、このような複雑で大きなリスクを伴う意思決定の質を保証することは、私たちの責任であると考えています。 この記事では、群衆の知恵と集団思考の概念を紹介することで、集団意思決定の潜在的な利点と脆弱性の両方について論じる。 その上で、集団思考を最小限に抑え、群衆の知恵を活用するために、教育的集団意思決定において簡単に実践できる12のヒントを、エビデンスに基づいて提供する。
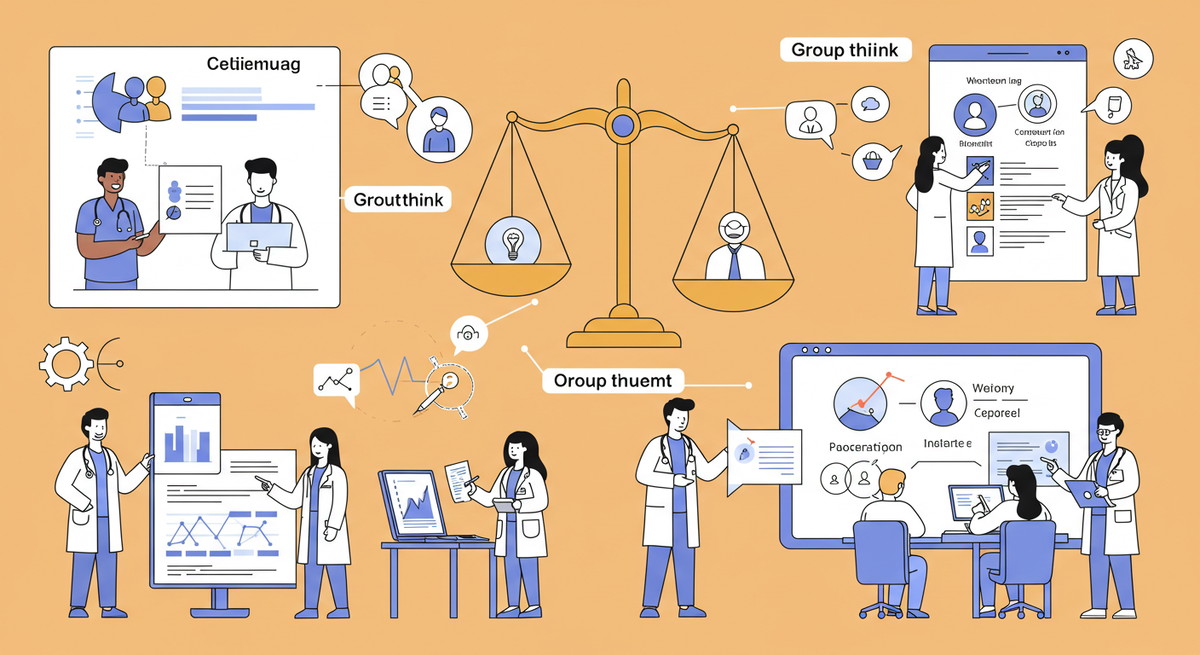
背景
- 医学教育では複雑かつ重要な決定(学生の進級や改善計画など)に集団意思決定(GDM)が頻繁に用いられている
- 集団意思決定は個人の決定よりも優れていると一般的に考えられているが、これは必ずしも保証されていない
- 集団は「集合知(wisdom of the crowd)」の恩恵を受ける可能性がある一方で、「集団思考(groupthink)」という落とし穴にも陥りやすい
集合知と集団思考
- 集合知:集団が持つ集合的知識の力。例えば、Francis Galtonの「牛の体重実験」では、800人の推測の中央値が実際の重さにきわめて近かった
- 集団思考:集団の結束性を維持するために同調性を優先し、最適ではない決定に至る現象。自己検閲や批判的思考の欠如などが特徴
12のヒント
1. 適切なリーダーを見つける(または適切なリーダーになる)
- リーダーシップスタイル: 水平的階層内での権威あるリーダーシップが最も効果的
- 必要な特性:
- トピックに関する深い知識
- 集団意思決定プロセスへの精通
- メンバーからの尊敬
- 実践例:
- 学部医学教育能力委員会(UME CC)の議長は、評価と改善に関する経験と知識、そして集団機能と意思決定に関する理解に基づいて選出
- 非投票メンバーとしての位置づけにより、水平的階層の確立と他者の決定への潜在的影響の最小化
2. グループメンバーが集団思考の特徴を認識できるようにする
- 教育的アプローチ:
- 実装方法:
3. 集合知を促進し、集団思考を抑制する集団文化を確立する
- 理想的文化:
- 合意よりも議論、討論、個人の意見表明を優先
- 水平的階層の枠組み内で構造化
- 参加と個性を促進する権威あるリーダーによる指導
- 心理的安全性の確立:
- 実装方法:
- 参照条件文書(TOR)の作成:構造、価値観、グループの目標を概説
- ジュニアメンバーの能力強化に焦点を当てる
- 包括的リーダーシップを実践する
4. メンバーの多様性を通じて集合的知識と視点を最大化する
- 多様性の重要性:
- 集団構成は決定の質を決定する最も重要な要因の一つ
- 多様なメンバーはより大きな情報、知識、経験、視点のプールを提供
- 各個人の潜在的バイアスは異質な視点のバランスを通じて最小化
- 多様性の次元:
- 実践的考慮事項:
- 多様性を最大化するためのメンバーシップ基準を使用
- 多様性が限られている場合は、割り当てられた反対意見(ヒント10)が特に重要
5. 会議の成功のための構造化
- 会議形式:
- 可能な限り対面会議を優先(バーチャル会議よりも効果的)
- 対面会議はエンゲージメントを促進し、社会的手抜きを最小化し、コミュニケーションを改善
- 会議の頻度と内容:
- 一度に多くの決定を「処理する」傾向に対抗
- 最適な情報共有と充実した動的な議論のために、一度の会議での決定数を減らす
- 認知的過負荷と疲労を防ぐ
- 実践例:
- より頻繁な会議を開催し、各会議での集団決定を少なくする
- 構造化された議題を会議前に配布
- メンバーが議論事項について考え、独自の意見や質問を生成する時間を与える
- 議題に「質問/コメント」セクションを含めることで全ての視点が共有/代表されるようにする
6. グループの決定ニーズを特定し、それらが満たされるようにする
- 決定ニーズの定義:
- 決定の質に悪影響を与える可能性のある情報の不足
- 研究知見:
- 集団決定の質は、共有された情報よりも未共有の情報の量によって決まる
- 「共有情報バイアス」: 集団は未知の情報を認めるよりも、すでに知られていることに焦点を当てる傾向がある
- 個人と集団のニーズ:
- 各個人は独自の決定ニーズを持つ
- 集団のニーズは各個人の過去の経験、実践スタイル、個人的価値観、リスク回避レベルなどの集合的なダイナミクス
- 実践的実装:
7. 明確で明示的な決定ルールを確立する
- 決定ルールの定義:
- 集団が決定に至るプロセス
- 心理学文献では「社会的決定スキーム」として反映
- 一般的な決定ルール:
- 合意: 結果の広範な受容性の達成が特徴(全員が同意する必要はないが、全員が選択を受け入れる必要がある)
- 全会一致: すべてのメンバーが反対意見の欠如または支持の明確な確認を通じて決定を支持する必要がある
- 多数決投票: 50%以上が「勝利」する
- 範囲投票: 各参加者が選択肢をランク付けし、最高スコアの選択肢が「勝利」
- 複数票: 多数決に似ているが、一つのオプションに50%以上の参加者が同意する必要なく、最大票数のオプションが勝利
- 実装上の課題:
- 決定ルールは通常暗黙的であり、不一致や対立がある場合にルールから「逸脱」するリスクがある
- 例: 研修医の改善計画に関する不一致がある場合、グループは同意しなくても「最も声の大きい」または最も先任のメンバーに従う可能性がある
- 社会的ネットワーク影響理論: 他のグループメンバーの選好の重み付けられた統合後の個人の態度変化または決定修正を説明する認知プロセス
- 推奨事項:
- 決定ルールは基礎的側面であり、明確で明示的で尊重される必要がある
- 委員会の参照条件文書に合意された決定ルールを含める
8. 機密性を確保する
- 機密性の重要性:
- グループメンバー間の自由で検閲されない議論を促進
- 議論される人々を保護
- 実践的アプローチ:
- 機密性を暗黙または想定しない
- 各会議の開始時に議論の機密性について参加者に注意を促す
- 参照条件文書と機密性に関連する会議手順にこれを反映させる
- 具体的なガイドライン例:
- 会議の録音禁止
- 議事録は特定のメンバーのみが作成し、他のメモは作成または収集しない
- 議事録は会議後にメンバーのみに配布し、それ以外には共有しない
- 会議中の議論は機密
- 匿名投票の使用:
- 各メンバーが投票を直接リーダーに提出し、リーダーのみがメンバーの個別決定を知る
9. 戦略的に議論を促進しシーケンスする
- 議論の構造化の目的:
- すべてのメンバーが貢献し、同調性の影響を減らすように促す形式の確立
- 推奨アプローチ:
- 議論をシーケンスして促進し、すべてのメンバーが意見を述べられるようにする
- ジュニアメンバー(または発言の少ないメンバー)から始め、自己検閲を避ける
- 各メンバーが発言し、平等な時間を与えることで説明責任を高め、社会的手抜きの効果を減らす
- 追加的利点:
- 集団内の「大きな声」の影響を最小化
- すべてのメンバー間で時間と貢献のバランスを取る
- 反対意見の欠如による想定された合意を回避
10. 割り当てられた反対意見を活用する
- 割り当てられた反対意見の定義:
- 批判的思考や議論を促進するために意図的に反対の見解を提供すること(「悪魔の代弁者」としても知られる)
- 効果:
- 集団意思決定に有益であることが示されている
- 集団同調性への高いモチベーションの問題を克服
- 役割が割り当てられるため、個人を危険にさらすことなく健全な不一致を奨励
- 実装方法:
- 会議前に、グループリーダーによって一人のグループメンバーにこの役割を割り当てる(会議の議題に反映)
- 行われる各決定に対してこの役割を割り当てる
- すべてのメンバー間で役割を継続的にローテーション(各メンバーが「悪魔の代弁者」を務める順番を取る)
- 追加的利点:
- 議論と不一致を優先するグループ文化の創造(ヒント3)
- 決定が集団の決定ニーズを満たすことを確認するために情報共有が批判的分析を通じて最適化されるよう支援(ヒント6)
- 実際の考慮事項:
- 文献によれば、真の反対意見は割り当てられたものよりも効果的である可能性があるが、高度に同調した集団ではこのようなプロセスの役割がある
11. メンバーの説明責任を高め、社会的手抜きを最小限に抑え、エンゲージメントを高める
- 社会的手抜きの定義:
- 個人が一人で作業する場合よりも、プロセスや決定において少ない努力や作業を投入する状況(Köhler効果の反対)
- 寄与要因:
- 識別可能性の欠如: バーチャル会議
- 説明責任の欠如: グループ内での定義された役割の欠如
- グループ内での作業や決定に対するクレジットを得る能力の欠如
- 表出形態:
- 提案された決定に同意しない場合でも、意見を表明しない
- 不一致があるにもかかわらず、想定された合意または全会一致を導く
- 対策:
- 説明責任を高めるための役割の割り当て
- 識別可能性を高めるための対面会議
- 各人が決定に対する合意または反対を明示的に表明することを要求(沈黙を支持と見なさない)
- グループ内での個人の努力や貢献を認識
12. 定期的なグループ監査を実施し、集団決定のプロセスと結果が許容可能であることを確認する
- 監査の定義:
- 特定のプロセスと結果の体系的レビュー
- 監査の重要性:
- 集団の意思決定プロセスの自然な傾向は集団思考に傾く
- より少ない労力で済み、多くの集団では個々のメンバーにとってより安全
- 集団極性化の問題:
- 集団の決定が集団内の個人が独立して行う決定よりも極端になる現象
- リスク方向(リスキーシフト)または慎重方向(慎重シフト)に向かうことがある
- 集団の高い同調性、共有された見解、責任の拡散がこれに寄与
- 例: 高度に同調し、構成が同質で、個々の説明責任が低い集団は、より厳しい決定結果(例: 研修医の解雇)に頻繁に傾く可能性がある
- 監査アプローチ:
医学教育における集団意思決定の具体的応用例
入学委員会
- 多様性の確保: 地理的に異なる施設、異なる実践領域、コミュニティとアカデミックの両方の職業プロファイル、様々なキャリアステージの教員を含む
- 匿名投票: 機密性を高め、同調圧力を減らすために実施
能力委員会(Competency Committee)
- リーダー選出: 評価と改善に関する経験と知識、および集団機能と意思決定の理解に基づく
- 教育的アプローチ: 会議開始時の集団意思決定の概要説明(年2回程度)
- シミュレーション: 集団思考に関するシミュレーションと講義
学術再評価委員会
- 決定ニーズの特定: EPA達成、総括試験スコア、OSCE成績、プロフェッショナリズム領域のパフォーマンス指標などの必須データリスト
- テンプレート使用: 各学術再評価のための情報収集と議論を導くテンプレート
レジデンシー研修委員会
- 割り当てられた反対意見: 専門プログラムへのレジデントまたはフェローのランク付けを決定する際に実装
- ロールローテーション: すべてのメンバーが「悪魔の代弁者」役を順番に担当
結論
集団意思決定は、適切に実行された場合、個人の決定よりも優れた結果をもたらす可能性がありますが、これは保証されていません。医学教育における多くの高リスク決定が集団で行われていることを考えると、これらのプロセスを最適化することが不可欠です。上記の12のヒントは、集合知を活用し集団思考を最小限に抑えるための実用的かつ証拠に基づいた戦略を提供しています。しかし、医学教育における集団意思決定に関するさらなる研究が必要であり、現在の理解の多くは他分野の研究から推測されたものです。